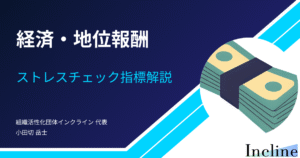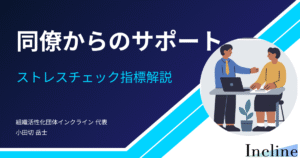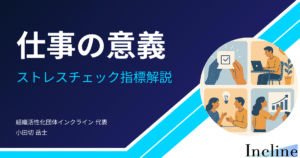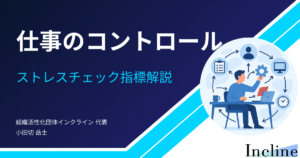シリーズ「ストレスチェック指標解説」では、新職業性ストレス簡易調査票(80項目版;以降「新調査票」)[1]で使用されている各指標を学術的な観点で掘り下げ、職場・組織としてできる対策のポイントを解説していきます。
今回は「家族・友人からのサポート」です。
質問項目
「家族・友人からのサポート」は、新調査票の「仕事の資源(部署レベル)」領域に含まれる指標で、以下3問で構成されています。
- 次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか?(配偶者、家族、友人等)
- あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか?(配偶者、家族、友人等)
- あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいてくれますか?(配偶者、家族、友人等)
この項目は、職場外のプライベートな人間関係から得られる、精神的な支えや困ったときの具体的な援助に焦点を当てています。
関連する学術概念
一口に「家族・友人からのサポート」といっても、上述の質問項目からしか情報が得られません。ここからは「家族・友人からのサポート」に関連する学術概念を参照し、この指標を深掘りしてみましょう。
例えば、「家族・友人からのサポート」に関連する概念には以下のようなものがあります。
配偶者からのサポート(Spousal Support)
配偶者からのサポートは、配偶者や親愛なパートナーから提供されるサポートを表します[2]。配偶者からのサポートを多く受けている人は、自分のパートナーが仕事の成功を共に喜び、困難な時には親身に相談に乗ってくれる、人生における最高の味方だと感じています。
配偶者からのサポートが多いと、結婚生活への満足度・主観的ウェルビーイングの向上、キャリア成功につながることなどが分かっています[3][4][5]。
結束型ソーシャル・キャピタル(Bonding Social Capital)
結束型ソーシャル・キャピタルは、家族や親しい友人といった、同質的な関係性から得られる、強固で緊密な資源を表します[6]。結束型ソーシャル・キャピタルが豊富な人は、家族や親友とは固い絆で結ばれており、いつでも無条件に頼ることができると感じています。
結束型ソーシャル・キャピタルには相反する2つの影響があります。健康状態の自己評価孤独感の緩和などポジティブな効果がある一方で、集団内での過度な義務感や排斥に対するストレスの上昇、相互依存を助長するなどのリスクがあることも分かっています[7][8]。
家庭から仕事へのエンリッチメント(Family-to-Work Enrichment)
家庭から仕事へのエンリッチメントは、家庭での役割で得られた経験や資源(スキル、視点、ポジティブな気分、サポートなど)が、仕事という別の役割における生活の質やパフォーマンスを向上させる度合いを表します[9]。家庭から仕事へのエンリッチメントができている人は、家族と過ごすことで得られる安らぎや楽しさが、仕事への活力となり、より良いパフォーマンスを発揮できています。
家庭から仕事へのエンリッチメントが高いと、仕事に対する満足感・組織に対する愛着感・仕事のパフォーマンスの向上につながることが示されています[10]。
研究知見から考える対策への手がかり
ここで質問です。集団分析結果で「家族・友人からのサポート」が良くない部署があった場合、どうすれば良いでしょうか?職場内の話ではないので、現実的に対処することが難しい場合もありますし、アプローチの幅が質問項目だけに限られてしまいます。
ここでは、研究知見を参照することで、質問項目以外のアプローチも探っていきたいと思います。
配偶者からのサポートの研究から
配偶者からのサポートを扱った研究では、以下のような条件下において、配偶者から支援されている感覚が促進されることが分かっています。
- 家庭支援的な上司行動が多い:上司が、部下の家庭生活を尊重するような支援を行っていると、部下は具体的に勤務時間を調整出来たり、家庭での問題を安心して話せたりするため、部下のワークライフバランスがとりやすくなることが分かっています[11]。結果として家庭や友人からのサポートの増加につながるといえるでしょう
- 業務負荷が管理可能で、役割葛藤が少ない:相手の持つ経験や能力への信頼があることで、仕事上の判断や責任を家族・友人に委ねられたり、個人的な悩みや感情を共有できたりすると、自己開示が促され、他者が支援の必要性に気づきやすくなったり、感情的・実務的な支援が自然発生しやすくなることが分かっています[12]。
- 職務上の裁量権が高い:自身の仕事の進め方に対するコントロール権は、従業員がより効率的に仕事を進めることを可能にし、結果として家族のために使える時間を生み出す可能性が示唆されています[13]。
結束型ソーシャル・キャピタルの研究から
結束型ソーシャル・キャピタルを扱った研究では、以下のような条件下において、結束型ソーシャル・キャピタルを促進できることが分かっています[14]。
- 雇用の安定性が高く、組織が安定していること:信頼というソーシャル・キャピタルの根幹は、長期間にわたる安定的で予測可能な相互作用を通じて構築されるため、雇用の安定性が関係の継続性を保証し、従業員が安心して同僚との関係に投資することを可能にするため、結束型ソーシャル・キャピタルが高まることが示されています[15]。
- 信頼、公正性、互恵性に基づいた組織文化があること:ソーシャル・キャピタルは共有された規範や価値観、そして互恵性から生まれるものであり、組織が公正な方針や透明性の高いプロセスを通じて信頼性を示すことで、従業員が安心して互いを信頼し、支援し合える心理的に安全な環境が醸成されるため、結束型ソーシャル・キャピタルが高まることが示されています[16]。
- 従業員間の相互作用と協働の機会が豊富にあること:人間関係は相互作用を通じて形成されるものであり、チームでのプロジェクト遂行や非公式な交流の場といった、従業員が頻繁に接点を持つ機会が構造的に提供されることで、互いの理解が深まり、信頼関係が構築されるため、結束型ソーシャル・キャピタルが高まることが示されています[17]。
家族から仕事へのエンリッチメントの研究から
家族から仕事へのエンリッチメント扱った研究では、以下のような条件下において、家族から仕事へのエンリッチメントが高まることが分かっています。
- スキルの多様性、タスクの重要性が高いこと:職務が多様なスキルを必要とし、その成果が重要であると認識されることで、仕事そのものが従業員にとってより魅力的で有意義なものとなり、ポジティブな感情の「獲得サイクル」が生まれるため、家族から仕事へのエンリッチメントが高まることが示されています[18]。
- 支援的な同僚関係が存在すること:信頼できる同僚との支援的な関係が、従業員に職場内での社会的な資源と心理的な安全性を提供し、家庭での役割や経験を職場でオープンに話せる環境を作ることで、家庭のアイデンティティが職場で肯定されるため、家族から仕事へのエンリッチメントが高まることが示されています[19]。
- 家族を支援する組織の方針と文化があること:柔軟な勤務時間制度といった方針や、それを奨励する文化が、組織が従業員を家庭の役割を持つ一人の人間として尊重しているという強力なシグナルとなり、役割葛藤を低減させ、信頼関係を醸成するため、家族から仕事へのエンリッチメントが高まることが示されています[20]。
対策のポイント
以上の研究知見に基づくと、実際にはどのような対策が考えられるでしょうか。以下、そのポイントです。
働き方の柔軟性を高め、時間的・精神的余裕を創出する
従業員が家族や友人と良好な関係を築き、必要な時にサポートを得るためには、そのための「時間」と「心の余裕」が不可欠です。過度な業務負荷や長時間労働は、これらを奪ってしまいます。
研究知見が示すように、従業員自身が仕事の進め方をコントロールできる「職務上の裁量権」を高めたり、柔軟な働き方を認めたりすることが有効です。具体的には、フレックスタイム制度やテレワークの導入・利用促進、個々の業務量の適正化などが挙げられます。こうした取り組みは、従業員が家族のイベントに参加したり、友人と会う時間を作ったりすることを物理的に可能にします。結果として、仕事と私生活のバランスが改善し、心の余裕が生まれ、家族や友人との関係性を育む土台ができます。
支援的な組織文化を醸成し、心理的安全性を確保する
職場の人間関係や組織文化も、従業員のプライベートなサポート体制に大きな影響を与えます。特に、上司や同僚の理解と支援は極めて重要です。
例えば、「家庭支援的な上司」がいる職場では、従業員は子どもの急な発熱といった家庭の事情を安心して相談でき、仕事の調整がしやすくなります。これは、上司が部下の家庭生活を尊重し、支援する姿勢を示すことで実現します。また、普段から同僚間で業務外のコミュニケーションが活発で、互いの状況を理解し合える「支援的な同僚関係」も、困った時にお互い様として仕事をカバーし合う雰囲気を生み出します。職場が「プライベートを尊重し、いざという時には配慮する」という安心感のある場所になることで、従業員のストレスは緩和され、間接的に家族や友人との良好な関係を維持する力となります。
仕事のやりがいを高め、公私の好循環(エンリッチメント)を促す
意外に思われるかもしれませんが、仕事そのものの魅力ややりがいを高めることも、「家族・友人からのサポート」を豊かにする上で重要です。これは「家庭から仕事へのエンリッチメント」の逆のサイクル、すなわち「仕事から家庭へのエンリッチメント」を促すことにつながります。
従業員が自分の仕事に重要性を感じ、多様なスキルを活かせていると実感できると、仕事に対する満足感や達成感が高まります。その結果得られるポジティブな気分や活力は、家庭に持ち帰られ、家族との関係にも良い影響を与えます。例えば、仕事でいきいきしている親の姿は、子どもにとっても良い刺激になるでしょう。仕事の充実が私生活の充実を生み、そして私生活の充実がまた仕事のパフォーマンスを高める。このような公私の好循環を創り出すことで、従業員はより豊かな人生を送り、結果として家族や友人からも力強いサポートを得られるようになるのです。
公正な組織運営で、従業員との信頼関係を築く
従業員が安心してプライベートなサポートネットワークを頼るためには、その土台として、働く組織そのものへの信頼感が欠かせません。研究では、ソーシャル・キャピタルの根幹は「信頼」「公正性」「互恵性」にあるとされています。具体的には、評価や処遇、情報共有などが特定の個人に偏ることなく、公正かつ透明に行われていることが重要です。
組織の運営方針が一貫しており、「この会社は従業員を誠実に扱ってくれる」という信頼感があれば、従業員は安心して組織に帰属し、同僚との間にも信頼関係を築きやすくなります。この組織レベルでの信頼が、従業員の心理的な安定につながり、私生活における人間関係にも良い影響を及ぼすのです。
雇用の安定とキャリアへの展望で、将来への安心を提供する
従業員とその家族にとって、最も根源的なセーフティネットの一つが「雇用の安定」です。経済的な不安は、家庭内のストレスを増大させ、家族関係を悪化させる大きな要因となり得ます。研究でも、安定した雇用が長期的な人間関係の構築を可能にし、ソーシャル・キャピタルを高めることが示されています。企業が安定した雇用を維持し、従業員が将来のキャリアパスを描けるよう支援することは、従業員の生活基盤を守る究極のサポートと言えるでしょう。この長期的な安心感が、従業員の精神的な余裕を生み、家族や友人との揺るぎない関係を築く上での強力な基盤となります。
終わりに
「家族・友人からのサポート」は、ストレスチェックの数ある指標の中でも、特にプライベートな領域に関わる項目です。そのため、集団分析の結果が思わしくなかったとしても、「職場としてはどうしようもない」と感じてしまうかもしれません。
しかし、今回ご紹介したように、学術的な研究知見を紐解くと、職場環境や働き方が、従業員の私生活におけるサポートネットワークの質に間接的に、しかし確実に影響を与えていることがわかります。
職場の対策が目指すべきは、従業員の私生活への直接的な介入ではありません。目指すべきは、従業員が大切な家族や友人との絆を育み、いざという時に頼れる関係性を維持するための「時間的・精神的な余裕」と「将来への安心感」を提供することです。
仕事(ワーク)と私生活(ライフ)は、対立するものではなく、相互に影響を与え合うものです。職場の環境が改善され、従業員がいきいきと働くことができれば、そのポジティブな影響は家庭にも波及し、逆に家庭でのサポートが仕事の活力源となります。
従業員が豊かなサポートネットワークを持っていることは、個人の幸福(ウェルビーイング)を高めるだけでなく、困難な状況からの回復力(レジリエンス)を高め、結果として組織全体の生産性向上にもつながります。
脚注
[1] 新職業性ストレス簡易調査票は、無料で閲覧可能です:東京大学大学院医学系研究科デジタルメンタルヘルス講座. (2012). 新職業性ストレス簡易調査票の公表について
[2] Iwasa, H., Yoshida, Y., & Ishii, K. (2024). Association of Spousal Social Support in Child-Rearing and Marital Satisfaction with Subjective Well-Being among Fathers and Mothers. Behavioral Sciences, 14(2), 106.
[3] Iwasa, H., Yoshida, Y., & Ishii, K. (2024). Association of spousal social support in child-rearing and marital satisfaction with subjective well-being among fathers and mothers. Behavioral Sciences, 14(2), 106.
[4] Feeney, B. C., & Van Vleet, M. (2016). Daily goal progress is facilitated by spousal support and promotes psychological, physical, and relational well-being throughout adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 111(3), 334–355.
[5] Amin, A. M., et al. (2017). Spousal support and subjective career success: The role of work-family balance and career commitment as mediator. Jurnal Pengurusan, 50, 133-144.
[6] Coffé, H., & Geys, B. (2007). Toward an empirical characterization of bridging and bonding social capital. Nonprofit and voluntary sector quarterly, 36(1), 121-139.
[7] Kim, D., Subramanian, S. V., & Kawachi, I. (2006). Bonding versus bridging social capital and their associations with self rated health: a multilevel analysis of 40 US communities. Journal of Epidemiology and Community Health, 60(2), 116–122.
[8] Salehi, N., Ehrlich, C., Kendall, E., & Sav, A. (2019). Bonding and bridging social capital in the recovery of severe mental illness: a synthesis of qualitative research. Journal of Mental Health, 28(3), 331-339.
[9] Greenhaus, J. H., & Powell, G. N. (2006). When work and family are allies: A theory of work-family enrichment. Academy of management review, 31(1), 72-92.
[10] Stepanek, S., & Paul, M. (2022). Umbrella summary: Work-family enrichment. Quality Improvement Center for Workforce Development.
[11] Greenhaus, J. H., Ziegert, J. C., & Allen, T. D. (2012). When family-supportive supervision matters: Relations between multiple sources of support and work–family balance. Journal of vocational behavior, 80(2), 266-275.
[12] Crain, T. L., & Hammer, L. B. (2013). Work–family enrichment: A systematic review of antecedents, outcomes, and mechanisms. Advances in positive organizational psychology, 303-328.
[13] Lapierre, L. M., Li, Y., Kwan, H. K., Greenhaus, J. H., DiRenzo, M. S., & Shao, P. (2018). A meta‐analysis of the antecedents of work–family enrichment. Journal of organizational behavior, 39(4), 385-401.
[14] Chen, Z. (2018). A literature review of team-member exchange and prospects. Journal of Service Science and Management, 11(04), 433.
[15] Parzefall, M. R., & Kuppelwieser, V. G. (2012). Understanding the antecedents, the outcomes and the mediating role of social capital: An employee perspective. Human Relations, 65(4), 447-472.
[16] Oliveira, Á. F., Gomide, S., & Poli, B. V. (2020). Antecedents of well-being at work: Trust and people management policies. RAM. Revista de Administração Mackenzie, 21(1), eRAMD200105.
[17] Claridge, T. (2018). Functions of social capital–bonding, bridging, linking. Social capital research, 20(1), 1-7.
[18] Badri, S. K. Z., & Panatik, S. A. (2013). Job Characteristics as the Antecedents of Work-to-family Enrichment: A Literature Review. Journal of Social and Development Sciences, 4(8), 394.
[19] 脚注13と同じ
[20] 脚注13と同じ
執筆:小田切岳士(組織活性化団体インクライン 代表)
公認心理師、ストレスチェック実施者資格保有。同志社大学心理学部卒業、京都文教大学大学院 博士課程前期修了(臨床心理学 修士)。株式会社ビジネスリサーチラボ フェロー。新卒では、企業向けメンタルヘルスサービスを提供する企業に入社し、個人カウンセラー・ストレスチェックコンサルタントに従事。その後、メンタルヘルス以外の知見を広げるべく株式会社ビジネスリサーチラボに入社。在職中に組織活性化団体インクラインを設立。ゲーム開発会社の人事を経験後、ビジネスリサーチラボ社に出戻り入社。これまでに、ストレスチェックに関する人事・産業保健部門向けのコンサルティングや、管理職・一般社員層を対象とした職場活性化ワークショップを、延べ30社・50組織以上に提供。また、人事・組織領域における学術研究レビューも100テーマ以上手がけ、理論と実務の橋渡しを行ってきた。日本産業衛生学会および日本産業精神保健学会では、それぞれ優秀演題賞を受賞。