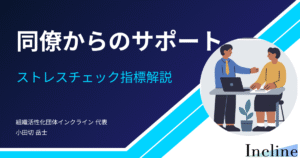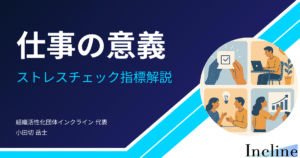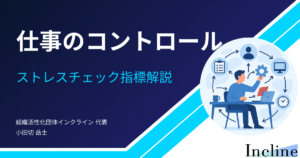シリーズ「ストレスチェック指標解説」では、新職業性ストレス簡易調査票(80項目版;以降「新調査票」)[1]で使用されている各指標を学術的な観点で掘り下げ、職場・組織としてできる対策のポイントを解説していきます。
今回は「経済・地位報酬」です。
質問項目
「経済・地位報酬」は、新調査票の「仕事の資源(部署レベル)」領域に含まれる指標で、以下の質問で構成されています。
- 自分の仕事に見合う給料やボーナスをもらっている
この項目は、自分の仕事の貢献度や遂行レベルが、給与やボーナスといった経済的な対価に適切に反映されているかという納得感に焦点を当てています。
関連する学術概念
一口に「経済・地位報酬」といっても、上述の質問項目からしか情報が得られません。ここからは「経済・地位報酬」に関連する学術概念を参照し、この指標を深掘りしてみましょう。
例えば、「経済・地位報酬」に関連する概念には以下のようなものがあります。
報酬水準満足度 (Pay Level Satisfaction) [2]
報酬水準満足度は、従業員が自身の給与額そのものに対して抱く、肯定的または否定的な感情の度合いを表します。報酬水準満足度が高い人は、自分の仕事内容や責任に見合った、納得のいく給与をもらっていると感じています。
報酬水準満足度が高いと、離職しようと思う意思の低下、実際の離職の減少、客観的な職務パフォーマンスの向上などにつながることなどが分かっています。
分配的公正 (Distributive Justice)
分配的公正は、報酬、昇進、資源といった組織内での配分結果が、従業員の貢献度や努力に照らして公平であるかという個人の主観的な認識を表します[3]。分配的公正が確保されていると感じる従業員は、組織から尊重され、正当に評価されていると感じます。
分配的公正が高いと、組織との一体感・組織に対する自発的な貢献行動の増加、仕事をさぼるといった逸脱行動の減少につながることが分かっています[4][5][6]。
相対的剥奪感 (Relative Deprivation)
自身が属する社会で一般的、あるいは望ましいとされる資源や生活水準を享受できていない状態を表します[7]。相対的剝奪感が少ない人は、同僚や他部署の報酬と比較しても、自分の待遇が不当に低いとは感じず、自分の貢献は公正に評価されていると感じています。
相対的剥奪感が低い(相対的剥奪感を抱いていない)と、心身健康度の向上、組織との一体感の促進、自分が所属する組織以外への偏見の緩和などにつながることが示されています[8][9]。
研究知見から考える対策への手がかり
ここで質問です。集団分析結果で「経済・地位報酬」が良くない部署があった場合、どうすれば良いでしょうか?給与をすぐに上げるということは難しいですし、アプローチの幅が質問項目だけに限られてしまいます。
ここでは、研究知見を参照することで、質問項目以外のアプローチも探っていきたいと思います。
報酬水準満足度の研究から
報酬水準満足度を扱った研究では、以下のような条件下において、報酬水準満足度が促進されることが分かっています。
- 外部公平性が確保されている:自社の給与水準が労働市場における同業他社の同等職種と比較して競争力があることで、従業員は自身のスキルや貢献が市場価値に照らして公正に評価されていると認識するメカニズムが働き、給与水準満足度が高まることが示されています[10]。
- 内部公平性が確保されている:同じ組織内の同僚、特に同じ職務に従事する他者と比較して、自身のインプット(努力、スキル、責任)に見合ったアウトカム(給与)を得られていると知覚されることで、公平理論に基づき、公正な処遇を受けているという感覚が生まれ、給与水準満足度が高まることが示されています[11]。
- 報酬制度に関する透明性の高いコミュニケーションが行われている:給与体系の仕組みや昇給の基準、各職務の給与レンジなどが明確に説明されることで、従業員は報酬決定の論理的根拠を理解し、不透明さから生じる憶測や不信感が払拭されるため、給与制度・運用への満足度が高まることが示されています[12]。
分配的公正の研究から
分配的公正を扱った研究では、以下のような条件下において、分配的公正を促進できることが分かっています[13]。
- 貢献に基づく分配が行われている:組織の目標が生産性の最大化である場合に、個人の業績や努力といった貢献度に応じて報酬を分配することで、従業員は努力が報われるというインセンティブを感じ、その結果の配分を正当なものとして受け入れるため、分配的公正が高まることが示されています[14]。
- 状況に応じた分配原則が適切に適用されている:生産性向上、集団の調和、メンバーの福祉といった組織が追求する目標に応じて、それぞれ公平原則、平等原則、必要原則といった最も適合する分配ルールが一貫して適用されることで、その配分決定の正当性が従業員に理解され、納得感が高まるため、分配的公正が高まることが示されています[15]。
- 質の高い社会的交換関係が構築されている:従業員と組織の間に信頼や互恵性に基づく良好な関係性が存在することで、従業員は組織による報酬配分の決定をより好意的に解釈し、公正なものとして受け入れやすくなるため、分配的公正の知覚が高まることが示されています[16]。
相対的剝奪感の研究から
相対的剝奪感を扱った研究では、以下のような条件下において、相対的剝奪感が低下することが分かっています。
- 手続き的公正が確保されている:報酬や昇進の決定プロセスが透明で、一貫性があり、従業員に意見を述べる機会が与えられていることで、たとえ結果が不利なものであっても、その決定プロセス自体が公正であると納得しやすくなり、結果の不当性を感じにくくなるため、相対的剥奪感が低下することが示されています[17]。
- 過度な権利意識を持っていない:特定の結果を当然の権利と見なすのではなく、自身の貢献や状況を客観的に評価することで、期待した結果が得られなかった場合でも、それを「権利の侵害」ではなく「未達」として受け止めやすくなり、不当な剥奪であるという認識が抑制されるため、相対的剥奪感が低下することが示されています[18]。
- 集団間の協力関係や共通の目標を重視する:部署や職種といった自集団と他集団を対立的に捉えるのではなく、組織全体の目標達成に向けた協力者として認識することで、集団間の格差への固執が薄れ、友愛的剥奪感が生じにくくなるため、相対的剥奪感が低下することが示されています[19]。
対策のポイント
以上の研究知見に基づくと、実際にはどのような対策が考えられるでしょうか。以下、そのポイントです。
評価・報酬制度の「ものさし」を共有する
従業員が最も不満を感じやすいのは、「なぜこの評価で、この給与なのか」という理由が不透明な時です。これを防ぐためには、評価制度や給与テーブル、昇給・昇格の基準といった「ものさし」を明確にし、全従業員に公開することが不可欠です。評価基準が具体的で、誰にでも分かる言葉で説明されていれば、従業員は自分のどの行動が評価に結びつくのかを理解し、目標に向かって努力しやすくなります。これは研究知見で示された「報酬制度に関する透明性の高いコミュニケーション」や「手続き的公正」の確保に直結し、結果に対する納得感を大きく高めます。
公正な評価プロセスを徹底する
たとえ評価の「ものさし」が明確でも、その運用が評価者の主観や気分に左右されては意味がありません。評価プロセスに一貫性を持たせ、客観性を担保する仕組みを整えましょう。具体的には、評価者向けの研修を実施して評価基準の目線合わせを行ったり、評価決定の際には複数の評価者が関与する体制を築いたりすることが有効です。また、評価面談では、結果を伝えるだけでなく、従業員本人の自己評価や意見に真摯に耳を傾ける「意見表明の機会」を保障することが、「手続き的公正」の観点から極めて重要です。
自社の報酬水準を客観的に点検する
従業員は、自分の給与を社内の同僚(内部公平性)だけでなく、社外の同じような仕事をしている人(外部公平性)とも無意識に比較しています。自社の給与水準が、世間一般や同業他社と比較して競争力のある水準か、また、社内での役割や責任の大きさに応じた適切なバランスが取れているかを定期的に点検しましょう。もし課題が見つかれば、すぐに全てを是正するのは難しくとも、現状を把握し、将来的な改善計画を従業員に示すだけでも、組織の誠実な姿勢が伝わり、納得感の醸成につながります。
「金銭以外」の報酬の価値を伝える
「報酬」は給与やボーナスだけではありません。挑戦的な仕事を通じて得られる成長の機会、専門性を高めるための学習支援、個人の裁量が尊重される職場環境、キャリアパスの多様な選択肢なども、従業員にとって価値のある「非金銭的報酬」です。こうした金銭以外の報酬が、会社として従業員の貢献に応えるための重要な仕組みであることを、日頃から意識的に伝えることが重要です。それにより、従業員と組織の間に信頼関係(質の高い社会的交換関係)が築かれ、経済的な報酬への過度な固執が和らぎ、組織全体で協力していこうという意識が高まります。
丁寧な対話で「納得感」を育む
最終的に、「経済・地位報酬」の満足度は、従業員一人ひとりの主観的な「納得感」に大きく左右されます。制度を整えるだけでは十分ではなく、管理職とメンバーによる日々のコミュニケーションが決定的に重要です。なぜこの評価になったのか、会社は何を期待しているのか、あなたの貢献をどう見ているのか。1on1ミーティングなどの場で、こうした対話を丁寧に積み重ねることが、従業員の不満や疑問を解消し、会社への信頼を育みます。そして、「自分は正当に評価され、尊重されている」という感覚は、分配的公正や相対的剥奪感の観点からも、従業員のエンゲージメントと心の健康を支える土台となるのです。
終わりに
給与や評価といったテーマは、組織の中でも特にデリケートで、正面から向き合うことには困難が伴うかもしれません。しかし、ストレスチェックでこの指標のスコアが良くないということは、従業員からの「自分たちの貢献や働きが、どのように報われているのか知りたい、納得したい」という静かな、しかし切実な声の表れと捉えることができます。
ご紹介した5つの対策は、単にスコアを改善するための小手先のテクニックではありません。それは、従業員一人ひとりと向き合い、「公平性」と「透明性」を追求する対話のプロセスそのものです。従業員が「この組織は、自分を公正に評価し、大切にしてくれる存在だ」と感じられること。この信頼関係こそが、個人のパフォーマンスを最大限に引き出し、組織全体のエンゲージメントを高め、ひいては企業の持続的な成長を支える最も重要な基盤となるのです。
すぐにすべての制度を完璧に整えるのは難しいかもしれません。しかし、まずは自社の評価や報酬の仕組みについて関係者で話し合ってみる、あるいは日々のコミュニケーションの中で、部下の働きに対する感謝や承認を言葉にして伝えることから始めることができます。
脚注
[1] 新職業性ストレス簡易調査票は、無料で閲覧可能です:東京大学大学院医学系研究科デジタルメンタルヘルス講座. (2012). 新職業性ストレス簡易調査票の公表について
[2] Williams, M. L., McDaniel, M. A., & Nguyen, N. T. (2006). A meta-analysis of the antecedents and consequences of pay level satisfaction. Journal of applied psychology, 91(2), 392.
[3] Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86(3), 386–400.
[4] 脚注3と同じ
[5] Kumar, M., Singh, S., & Dalla, N. (2022). Perceived fairness in distributive justice and organization citizenship behavior: Examining the mediating role of gratitude. Frontiers in Psychology, 13, 956189.
[6] Krischer, M. M., Penney, L. M., & Hunter, E. M. (2010). Can counterproductive work behaviors be productive? It’s a matter of justice. Academy of Management Perspectives, 24(3), 101-102.
[7] Smith, H. J., Pettigrew, T. F., Pippin, G. M., & Bialosiewicz, S. (2012). Relative deprivation: A theoretical and meta-analytic review. Personality and Social Psychology Review, 16(3), 203-232.
[8] Kondo, N., Kawachi, I., Hirai, H., Kondo, K., & Subramanian, S. V. (2015). Relative deprivation and mortality: prospective cohort study in a Japanese older population. Journal of Epidemiology and Community Health, 69(7), 680-685.
[9] 脚注7と同じ
[10] Till, R. E., & Karren, R. (2011). Organizational justice perceptions and pay level satisfaction. Journal of managerial psychology, 26(1), 42-57.
[11] 脚注10と同じ
[12] Day, N. E. (2011). Perceived pay communication, justice and pay satisfaction. Employee relations, 33(5), 476-497.
[13] Chen, Z. (2018). A literature review of team-member exchange and prospects. Journal of Service Science and Management, 11(04), 433.
[14] Cook, K. S., & Hegtvedt, K. A. (1983). Distributive justice, equity, and equality. Annual review of sociology, 9(1), 217-241.
[15] 脚注14と同じ
[16] Svensson, G., Mpinganjira, M., & Roberts-Lombard, M. (2019). The antecedents and postcedents of satisfaction in business-to-business relationships in South Africa. South African Journal of Business Management, 50(1), 1-11.
[17] Smith, H. J., & Huo, Y. J. (2014). Relative deprivation: How subjective experiences of inequality influence social behavior and health. Policy insights from the behavioral and brain sciences, 1(1), 231-238.
[18] Smith, H. J., Pettigrew, T. F., Pippin, G. M., & Bialosiewicz, S. (2012). Relative deprivation: A theoretical and meta-analytic review. Personality and social psychology review, 16(3), 203-232.
[19] Christie, D. J., Wagner, R. V., & Winter, D. D. N. (Eds.). (2001). Peace, conflict, and violence. Prentice Hall.
執筆:小田切岳士(組織活性化団体インクライン 代表)
公認心理師、ストレスチェック実施者資格保有。同志社大学心理学部卒業、京都文教大学大学院 博士課程前期修了(臨床心理学 修士)。株式会社ビジネスリサーチラボ フェロー。新卒では、企業向けメンタルヘルスサービスを提供する企業に入社し、個人カウンセラー・ストレスチェックコンサルタントに従事。その後、メンタルヘルス以外の知見を広げるべく株式会社ビジネスリサーチラボに入社。在職中に組織活性化団体インクラインを設立。ゲーム開発会社の人事を経験後、ビジネスリサーチラボ社に出戻り入社。これまでに、ストレスチェックに関する人事・産業保健部門向けのコンサルティングや、管理職・一般社員層を対象とした職場活性化ワークショップを、延べ30社・50組織以上に提供。また、人事・組織領域における学術研究レビューも100テーマ以上手がけ、理論と実務の橋渡しを行ってきた。日本産業衛生学会および日本産業精神保健学会では、それぞれ優秀演題賞を受賞。